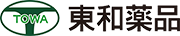-
Q&A
“てんかんがあるから”働けない?そんなことはありません。
てんかんがあると仕事はできない。そんな誤解が存在しますが、そんなことはありません。
確かに、航空機パイロットなどの一部職業には法律上、てんかん患者さんは就くことができませんが、多くの職業ではそのような制限はありません。個々の適性に合った職業を選ぶことができます。 詳しくは「どんな仕事?」
「てんかん」と一口に言ってもさまざまな症状があります。
てんかん発作は、大きな発作から小さな発作までさまざまであり、またどのような症状が現れるかひとりひとり異なります。 詳しくは「どんな病気?」
自分のてんかんについてどこまで知っていますか?
ひとりひとり症状が異なるため、一般的なことを知るよりも自分のてんかんがどのようなものかをしっかりと理解することの方が大切になります。 詳しくは「あなたのてんかんはどんなタイプ?」
職場に伝える?伝えない?自分の症状の特徴に合わせて考えましょう。
自分の症状が業務に影響するのか、伝えることで得られるメリットやサポートがあるのか、など自分にとって何が必要なのか検討しましょう。 詳しくは「職場とはどんな連携?」
仕事を長く続けるために普段の生活も大事にしましょう。
不規則な生活は発作が起きやすくなる原因にもなります。
仕事を長く続けるためには、忙しいときこそ規則正しい生活を心がけましょう。 詳しくは「どんなライフスタイル?」自分に合った働き方を探していきましょう。
利用できるサポートにはいろいろなものがあります。自分に合った働き方を探していきましょう。
また、ひとりで抱え込まずに、主治医や支援機関などにも相談してみましょう。 詳しくは「どんなサポート?」 -
どんな仕事?
てんかんがあると働けないの?
そんなことはありません。てんかんがあっても働いている人はたくさんいます。

「てんかんがある」ということだけにとらわれずに、自分の強みややりたいコトなども考慮しつつ、どのような就労を目指すのか考えてみましょう。
主治医などにも相談しながら、まずは前向きに検討してみましょう。

就労を支える3ポイント
● 自分の症状の理解
発作の種類、傾向、発作時の適切な対応法
● 治療の継続
定期的な受診、指示通りの服薬
● 日常生活の自己管理
規則正しい生活 など

仕事を選ぶ上で気を付けることは?
自分のてんかんに影響があるか、発作による危険があるかを検討しましょう。
発作でどのような症状が出るのか、服薬などで発作が止まっているのか、発作の引き金になるようなことがあるのか、などによって注意することが異なります。
また、発作が残っている場合も、日中に発作が起きてしまうのか、夜間にしか発作が起きないのか、ということも判断材料になります。
仕事によって自分のてんかんに悪影響がないか、発作によって危険が生じる可能性はないか、ということを検討しましょう。
例えば・・・
● 意識がなくなる発作がある場合
高所作業のような発作時のケガが考えられるものは避ける
● 発作以外の症状がある場合
記憶障害や抑うつ、不安といった症状があれば、精神科医などにも相談 など

仕事を始めたことで生活が不規則になったり、通院が難しくなったりすると、発作が悪化する要因にもなります。適切に治療を継続できるか、ということもぜひ考慮してください。
-
どんな病気?
てんかんってどんな病気?
発作を繰り返し起こす病気で、100人に1人いるといわれています。
てんかんは、脳の神経細胞の電気活動が一時的に乱れることによっててんかん発作が繰り返して起こる脳の慢性的な疾患であり、発作が脳の一部で起きる「焦点てんかん」と脳の全体で起きる「全般てんかん」に分けられます。

てんかんは、赤ちゃんからお年寄りまで誰でもいつでも発症する可能性があります。人口の100人に1人の割合でみられ、日本国内では約100万人のてんかん患者さんがいるといわれています。

どんな治療をするの?
基本は薬です。正しく飲んで、発作をコントロールしましょう。

抗てんかん薬はてんかん発作のタイプによって使い分けられているため、主治医は患者さんのタイプに合わせた薬を選んで、効果と副作用を確認しながら用量を調整しています。
安心して就労するためにも、薬は毎日きちんと飲みましょう。

薬は飲み忘れず、正しく飲みましょう
薬を飲み忘れてしまうと、発作が起きやすくなってしまいます。また、自己判断で減量したり、中止したりすると、症状を悪化させる可能性があります。
薬を飲み続けることによる心配事や副作用などで困ったことなどがあるときは、まず主治医に相談しましょう。
みんな似たような症状なの?
大きな発作から小さな発作までさまざまな症状があり、ひとりひとり違います。
同じ「てんかん」という疾患であっても、その発作はひとりひとり異なります。気を失って手足をガクガクとけいれんさせるような大きな発作から、数秒ほどボーっとして反応がなくなるような小さな発作まで幅広い症状があります。

わからないことがあると、人はより不安に感じやすいものです。自分のてんかんがどのようなタイプで、どのような特徴があるのか知ることが、安心して就労をする上での第一歩となるでしょう。
-
あなたのてんかんはどんなタイプ?
次の質問に対して、あなたはいくつ答えられますか?
答えられたものにチェックを付けていきましょう。


これらのことをあらかじめ説明しておけば、自分も周りの人もより安心できるでしょう。<不要なサポートの例>
- 短時間で発作が収まった場合の救急車
- 発作後の様子見のための早退 など

-
職場とはどんな連携?
てんかんがあると伝えないとダメ?
業務に影響があるか、サポートが必要かなどの自分の状況に合わせて検討しましょう。

ただし、事前に伝えておくことで、適切なサポートが得やすくなりますので、伝えることのメリットも考えて決めましょう。伝えた方が良いケース
- 発作が落ち着いておらず、発作時に適切な対応をお願いしたい場合
- 万が一の発作でも危険がないように業務内容を配慮してもらいたい場合 など

何を伝えたらいいの?
自分自身のてんかんについて具体的かつ短めに伝えましょう。
職場が特に知りたいのはあなたのてんかんがどのような症状で、どのようなサポートが必要なのか、必要でないのか、ということです。
『伝え方のポイント』を参考に、自分自身のてんかんについて、わかりやすく伝えましょう。伝え方のポイント
長い説明では、相手もなかなか理解しにくいものです。そして、誤解や不安の原因にもなりかねません。そのため、具体的でわかりやすく短めの説明が大切になります。 「あなたのてんかんはどんなタイプ?」の内容も参考に、あらかじめ伝える内容を決めておきましょう。
また、具体的な説明は相手に理解してもらいやすいだけでなく、自分の症状をきちんと把握して管理できているという好印象を与えて、安心感を感じてもらうことにもつながるでしょう。
-
どんなライフスタイル?
ついつい仕事が忙しくて・・・生活リズムが崩れてしまいます。
不規則な生活は発作の原因になります。忙しいときほど、生活のリズムを大切に。

規則正しい生活を送ることが、安心して仕事を続けるための基盤になります。忙しい時期こそ、意識して普段通りの生活リズムを送るようにしましょう。
運動はしてもいいの?
発作による危険がなければ普通に運動しても大丈夫です。
発作がコントロールできている場合や発作による危険がなければ、運動を制限する必要はありません。ただし、過度な疲労は発作の原因になりますので、適度に楽しむようにしましょう。
なお、発作によって生命に危険を及ぼすもの(ロッククライミング、ダイビングなど)は避けるようにしましょう。● 寝不足厳禁!! しっかり休みましょう

また、寝る前の食事、コーヒーなどのカフェイン飲料や、ベッドに入ってからのスマートフォンの使用などは睡眠の質を低下させるのでやめましょう。
● お酒の飲みすぎに注意しましょう

また、過度のアルコール摂取は睡眠を浅くし、てんかん発作を誘発する可能性もあります。飲みすぎないように注意しましょう。
● 発作の状況に合わせて、自宅でも安全対策を

例)発作が残っている場合- 料理のときになるべく火を使わない
- シャワー浴にする など

-
どんなサポート?
どのような就労サポートがあるの?
いろいろな制度があるので、自分の症状や環境に合わせて、
より良いものを活用しましょう。てんかんの症状がさまざまであるように、その働き方も一般就労のほかに、就労系障害福祉サービスを用いた福祉的就労などさまざまです。
服薬で発作がなく、仕事に影響しないのであれば、一般就労が可能でしょう。発作による不安があれば、福祉的就労から始め、自分の症状や環境に合わせて、一般就労を目指すのも良いでしょう。
サービスをうまく活用することで、てんかんと上手に付き合いながら働ける可能性も広がるでしょう。
障害者手帳の取得によって利用できるサービスが増えることもあります。手帳は常に表に出す必要もありませんので、あなたの症状や環境によっては、手帳の取得も検討してみてください。● 自動車運転について

道路交通法上、運転が可能な状況でも、抗てんかん薬を飲み忘れたときや発作が起きそうな不安があるとき、体調不良、睡眠不足のときなどは、運転を控えるようにしましょう。
自分だけでいろいろ調べるのは大変です。ひとりで悩まず、ぜひ相談しましょう。

まず、第一歩としては主治医や病院の地域連携室、ソーシャルワーカーなどに相談してみてはどうでしょうか。<その他の相談先>
- 市町村の障害福祉担当窓口
- 公共職業安定所(ハローワーク)
- 障害者就業 ・ 生活支援センター など