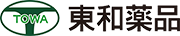- どんな症状?
- どんな病気?
- どんな治療?
-
どんな
ライフスタイル?
-
どんな症状?
人前で過度に緊張・不安を感じます。
下記のような症状を感じたことや、これらの状況を過剰に避けたことから、困った経験はありますか?
緊張や不安は誰でも経験するものですが、社交不安症(SAD)∗の場合はこれらの状況で感じる過剰な緊張や不安、恐怖から、これらを回避しようとする行動によって、社会生活に支障をきたし、困難を感じてしまいます。
∗SAD:Social Anxiety Disorder過度の緊張・不安を感じる
状況と症状
主な身体的症状 
性格の問題ではありません。
これらの症状によって生活に支障が出ていても、「性格だから」と考え、治療を受けずにいるケースが多くみられます。適切に治療を受けることで、不安感をやわらげ、症状とうまく付き合っていくことができるようになります。
上記のような状況で、強い緊張や不安、恐怖を感じ、次のようなことが起きているようであれば、社交不安症の可能性があります。- その状況をできるだけ回避したくなる
- 実際に、ときどき回避している
- 実際に、ほとんど回避している
- 回避によって、苦痛を感じている
- 回避によって、社会生活が困難になっている
該当する方は、まず医師に相談してみましょう。

-
どんな病気?
不安が強くなる状況を過度に避け、生活にも支障が出てしまいます。

また、過去の失敗経験をきっかけに、不安や緊張を過度に感じる傾向が強まるケースもあります。
1対1の場面でも影響がみられます。


脳の神経伝達物質のバランスが崩れていることが関連しています。
社交不安症のような症状は、性格の問題と捉えられていた時期がありました。不安になりやすい人の思考パターンの傾向は確かに見受けられますが、社交不安症は脳の神経伝達物質のバランスの崩れも関係していることがわかってきています。
特に「セロトニン」の減少が影響しているとされます。セロトニンが不足すると神経伝達がスムーズにできず、脳が過敏な状態になって、緊張や不安、恐怖を感じやすくなると考えられています。セロトニンのはたらき

-
どんな治療?
薬物療法と認知行動療法が基本です。
社交不安症の治療法は大きく2つに分けられます。ひとつは、薬の服用によって脳の神経伝達物質のバランスを整えるなどして、不安症状を改善させる「薬物療法」です。もうひとつは、不安を増強させてしまう思考パターンを、カウンセリングなどによって調整する「認知行動療法」です。
個々の症状に応じて、これら2つを組み合わせて治療し、過度な不安を徐々に軽減させていきます。
毎日服用する薬と、不安が強いときだけ服用する薬があります。
治療に用いる薬は、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)と呼ばれるものが基本になります。毎日服用することで不足しているセロトニンを増やして不安を感じにくくし、症状をやわらげていきます。
不安が特に強く、生活に支障が出そうなときは、一時的に不安を軽減する抗不安薬が用いられることもあります。SSRIの効果と副作用

不安が少なくなった後も、薬は継続して飲み続けましょう。

自己判断で薬をやめたり量を減らしたりせず、医師の指示通りに毎日服用を続けましょう。気になることがあれば、医師に相談しましょう。
認知行動療法では、受け止め方や不安への対処法をトレーニングします。
認知行動療法では、出来事に対する受け止め方や思考パターンといった「認知」と、それにどのように対処するかといった「行動」に対して、はたらきかけます。
社交不安症の人は、客観的な現実とは異なる否定的な「認知」によって、不安感を強くしてしまっているケースがあります。そのことに自身が気付き、考え方のクセを修正することによって「行動」をコントロールし、不安感や恐怖感を軽減できるようにトレーニングしていきます。
長年の経験や環境で身についた「認知」や「行動」を変えるには、誰でも時間がかかります。認知行動療法では、専門家とともにゆっくり時間をかけて、徐々に改善を目指します。
※認知行動療法は、必ず専門家の指導のもとで行ってください
認知行動療法の一例 ~ビデオフィードバック~

たとえばスピーチの場面で、本人は極度に緊張して不安でたまらなかったと思っていても、ビデオで見ると案外心配していたほどでもない、ということを本人に気付いてもらいます。客観的な現実との違いを確認し、否定的な自己イメージや考え方を変えることで不安感をやわらげ、行動の変化も促すという手法です。
「不安な状況でも自分らしさを発揮できる状態」を目指します。


-
どんなライフスタイル?
規則正しい生活を心がけましょう。

たとえば、毎朝なるべく決まった時間に起き、散歩や軽いジョギングなどの運動を定期的に行い、朝・昼・晩と三食きちんとバランスのよい食事をとり、夜も決まった時間に就寝して十分な睡眠をとるなど、生活のリズムを整え、強化するように心がけましょう。夜型の生活や睡眠不足、不規則な食事などは、避ける方がいいでしょう。
適度な運動で心も体もリフレッシュ。

ただし、やり過ぎは禁物です。脳も疲労して逆効果になる可能性があります。休憩をはさみながら、無理なくやっていきましょう。
ご家族の方へ
社交不安症は、単なる性格の問題ではありません。また、決して特別な病気でもありません。米国の調査で生涯有病率は12.1%と報告されています1)2)。
社交不安症の治療には、家族や周囲の人たちのサポートが大切です。ただ、過剰な心配や励まし、世話の焼きすぎは、かえって患者さんの負担になりかねません。患者さんの困りごとをよく理解した上で、できるだけいつも通りの自然な態度で接し、温かく見守るようにしましょう。
患者さんが苦手な場面でサポートが必要なときは、本人とよく話し合い、対処の仕方を一緒に考えていきましょう。心配なことがあれば、医師や専門家に相談しましょう。
患者さんにとって、安心して過ごせる環境はとても大事です。リラックスできる生活空間をつくることも、症状改善への大きなサポートとなります。
1)Kessler RC, et al. Arch Gen Psychiatry. 62(6): 593-602, 2005
2)Ruscio AM, et al. Psychol Med. 38(1): 15-28, 2008